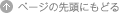гГЛгГ•гГЉгВє & и©±й°М
гБµгВЛгБХгБ®ж≠МгБДеЕµе£ЂгБѓж≠їгВУгБ†вА¶йШ™еП£гБХгВУжґЩгБЃжȶ决冱еСК
姙еє≥жіЛжИ¶дЇЙдЄ≠гАБгВљйА£иїНгБЃжНХиЩЬгБ®гБЧгБ¶гВЈгГЩгГ™гВҐгБЂжКСзХЩгБХгВМгАБдєЭж≠їгБЂдЄАзФЯгВТеЊЧгБ¶еЄ∞еЫљгБЧгБЯеТМж≠Ме±±зЬМж©ЛжЬђеЄВеВЈзЧНиїНдЇЇдЉЪдЉЪйХЈгГїйШ™еП£зєБжШ≠гБХгВУпЉИпЉШпЉХпЉЙгБѓгАБж©ЛжЬђеЄВдЄ≠е§ЃеЕђж∞С駮䪿еВђгБЃеЄВж∞СиђЫеЇІгБІгАБиЗ™гВЙгБЃжИ¶е†ідљУй®УгВТ冱еСКгБЧгАБйШ™еП£гБХгВУгБЃгАМдЇМеЇ¶гБ®жИ¶дЇЙгВТзє∞гВКињФгБХгБ™гБДгБІгБїгБЧгБДгАНгБ®гБДгБЖењГеЇХгБЛгВЙгБЃй°ШгБДгБМгАБиБіиђЫиАЕгБЃеЕ±жДЯгВТеСЉгВУгБІгБДгБЯгАВ
йШ™еП£гБХгВУгБѓжШ≠еТМпЉСпЉЩеєіпЉИпЉСпЉЩпЉФпЉФпЉЙгАБжЇАиТЩйЦЛжЛУйЭТе∞СеєізЊ©еЛЗйЪКгБЂеЕ•йЪКгБЧгБЯгБМгАБгБЩгБРгБЂе∞СеєіеЕµгБ®гБЧгБ¶дЄ≠еЫљгГїгВљйА£гБЃеЫљеҐГгБІиїҐжИ¶гАВй†≠гБЂиҐЂеЉЊгБЧгБ¶еЈ¶иА≥гБЃиБіеКЫгВТ姱гБ£гБЯгАВеРМпЉТпЉРеєіпЉИпЉСпЉЩпЉФпЉХпЉЙпЉШжЬИпЉТпЉТжЧ•гАБгВљйА£гБЃй£Ыи°МиИєгБМгАЭиНТеЯОгБЃжЬИгАЯгБЃжЫ≤гВТжµБгБЧгБ™гБМгВЙгАБжЧ•жЬђгБЃжХЧжИ¶гВТеСКгБТгАБжКХйЩНгВТињЂгБ£гБ¶гАБжНХиЩЬгБЂгБХгВМгБЯгАВгВЈгГЩгГ™гВҐгБІгБѓе§ЪгБПгБЃжИ¶еПЛгВТ姱гБДгАБйБОйЕЈгБ™еКіељєгБЂиАРгБИгБ¶гАБеРМпЉТпЉТеєіпЉСпЉТжЬИгАБдЄЗж≠їгБЂдЄАзФЯгВТеЊЧгБ¶еЊ©еУ°гБЧгБЯгАВ
гБУгБЃжЧ•гБЃеЄВж∞СиђЫеЇІгБІгАБйШ™еП£гБХгВУгБѓгАМжИ¶е†ідљУй®УпљЮдЄ≠гВљжИ¶пљЮе∞СеєіеЕµгБ®гБЧгБ¶гБЃе†±еСКгАНгБ®й°МгБЧгАБжЬђзЙ©гБЭгБ£гБПгВКгБЃгВЈгГЩгГ™гВҐгБЃгАЭйїТгГСгГ≥гАЯгВДгАБж±Їж≠їгБЃи¶ЪжВЯгБІжМБгБ°еЄ∞гБ£гБЯгАЭжИ¶еПЛе≠ШеСљжЙЛеЄ≥гАЯгБ™гБ©гВТжКЂйЬ≤гАВ
зЬМзЂЛзіАеМЧеЈ•ж•≠йЂШж†°гГїйЫїж∞ЧзІСгБЃеЕГжХЩиЂ≠гÿ汆ж∞ЄжБµеПЄгБХгВУпЉИпЉШпЉУпЉЙгВВгАБйШ™еП£гБХгВУгБЛгВЙдЊЭй†ЉгВТеПЧгБСгБ¶гАБгВЈгГЩгГ™гВҐгБІжИ¶еПЛгБЃйБЇдљУгВТгВљгГ™гБІйБЛгВУгБ†гВКгАБйЫ™дЄ≠гАБе≤©е°©гВТйБЛжРђгБЧгБЯгВКгБЩгВЛжЧ•жЬђеЕµгБЃеЖЩзЬЯгБ™гБ©гАБи®ИпЉФпЉФжЮЪгВТгГСгВљгВ≥гГ≥гБІгВєгВѓгГ™гГЉгГ≥гБЂжКХељ±гАВйШ™еП£гБХгВУгБѓзФЯгАЕгБЧгБДеЖЩзЬЯгВТи¶ЛгБ¶гВВгВЙгБДгБ™гБМгВЙгАБељУжЩВгБЃж®°жІШгВТиµ§и£ЄгАЕгБЂе†±еСКгБЧгБЯгАВ
дЊЛгБИгБ∞гАБйШ™еП£гБХгВУгБЃи®Љи®АгВТгВВгБ®гБЂгБЧгБ¶гАБеТМж≠Ме±±зЬМжХЩиВ≤еІФеУ°гБІзЂ•и©±дљЬеЃґгБЃдљРиЧ§еЊЛе≠РгБХгВУгБМдљЬгБ£гБ¶гБПгВМгБЯгАЭйїТгГСгГ≥гАЯгВТжКЂйЬ≤гБЧгБ™гБМгВЙгАБгАМгВЈгГЩгГ™гВҐгБІгБѓйЫґдЄЛпЉУпЉРеЇ¶гБЃзМЫзГИгБ™еѓТгБХгБЃдЄ≠гАБзЯ≥зВ≠е†АгВКгВДйЙДйБУеїЇи®≠гАБж£ЃжЮЧдЉРжО°гБ™гБ©йЗНеКіеГНгВТеЉЈгБДгВЙгВМгАБй£ЯгБєзЙ©гБѓгАБгБУгБЃгВИгБЖгБ™гАЭйїТгГСгГ≥гАЯгБЃгАБгБЭгВМгВВгАБгБЯгБ£гБЯдЄАеИЗгВМгБ®е°©гВєгГЉгГЧпЉСжЭѓгБ†гБСгАВе§ЪгБПгБЃжИ¶еПЛгБМй£ҐгБИгБ®еѓТгБХгБІжБѓзµґгБИгБ¶гАБеЗНеЬЯгБЃдЄКгБЂйЗОз©НгБњгБХгВМгБЊгБЧгБЯгАНгБ®гАБгБЭгБЃйБОйЕЈгБ™зФЯжіїгВТињ∞жЗРгАВгАМзІБгБѓе≤©е°©гВТйБЛгБґеКіељєгБЃйЪЫгАБгГЭгВ±гГГгГИгБЂе≤©е°©гВТйЪ†гБЧгАБжЭЊжЮЧгБЃжЭЊиСЙгВТгВАгБЧгВКеПЦгБ£гБ¶гАБе≤©е°©гВТгБЊгБґгБЧгАБеЩЫгБњгБЂеЩЫгБњгБ§гБґгБЧгБ¶гГУгВњгГЯгГ≥гВТеРЄеПОгБЧгБЊгБЧгБЯгАНгБ®гАБењЕж≠їгБІзФЯгБНжКЬгБДгБЯжЬЙжІШгВТи®Љи®АгБЧгБЯгАВ
гБЊгБЯгАБгАМеЕГжХЩеУ°гБ†гБ£гБЯиЛ•гБДеЕµе£ЂгБМгАБеО≥гБЧгБДеКіељєгБЛгВЙжИїгВЛгБ®гАБгБЖгВПгБФгБ®гБЃгВИгБЖгБЂзЂ•иђ°гАЭгБµгВЛгБХгБ®гАЯгВТж≠МгБ£гБ¶гБДгВЛгАВйИіжЬ®гБ®и®АгБЖеРНгБЃдЄ≠йЪКйХЈгБМгАЭгБУгВМгБѓгБКгБЛгБЧгБДгАВгБњгВУгБ™гАБдЄАзЈТгБЂж≠МгБ£гБ¶гВДгВМгАЯгБ®еСљдї§гАВзІБгБЯгБ°еЕ®еУ°гБІзє∞гВКињФгБЧж≠МгБ£гБЯгВВгБЃгБЃгАБгБ†гВУгБ†гВУжґЩе£∞гБЂгБ™гВКгАБж≠МгБЂгБѓгБ™гВЙгБ™гБЛгБ£гБЯгАВгБЭгВМгБІгВВиЛ•гБДеЕµйЪКгБѓе§Іе§ЙеЦЬгВУгБІгАБжШОгБСжЦєгБЂгБѓгАЭгБВгВКгБМгБ®гБЖгАЯгБЃи®АиСЙгВТжЃЛгБЧгБ¶дЇ°гБПгБ™гВКгБЊгБЧгБЯгАНгБ®и©±гБЧгАБгАМгБЭгБЃйБЇдљУгБѓгАБи°®гБЃеЗНеЬЯгБЂйБЛгБ≥гАБдїЦгБЃйБЇдљУгБЃдЄКгБЂз©НгБњдЄКгБТгБ¶гБДгБПгАВгБЭгБЃиЊЫгБХгБ®гБДгБЖгВВгБЃгБѓгАБдїКгБ™гБКењШгВМгВЛгБУгБ®гБМгБІгБНгБЪгАБеѓЭгБ¶гВВи¶ЪгВБгБ¶гВВиЊЫгБДгБІгБЩгАНгБ®и™ЮгБ£гБЯгАВ
гБХгВЙгБЂгАЭжИ¶еПЛе≠ШеСљжЙЛеЄ≥гАЯгВТжКЂйЬ≤гБЧгБ¶гАБељУжЩВгАБжИ¶еПЛгБЯгБ°гБЃйЦУгБЛгВЙгАМи™∞гБЛгБМжЧ•жЬђгБЂеЄ∞гВМгБЯгВЙгАБгВПгВМгВПгВМгБМеЕГж∞ЧгБЂе≠ШеСљгБЧгБ¶гБДгВЛгБУгБ®гВТгАБгБЬгБ≤еЃґжЧПгБЂдЉЭгБИгБ¶гБїгБЧгБДгАНгБ®и®АгБЖе£∞гБМдЄКгБМгВКгАБжЧІгГїгВљйА£еЕµгБМдљњгБ£гБ¶гБДгБЯгВїгГ°гГ≥гГИиҐЛгВТгБ≤гБЭгБЛгБЂеЕ•жЙЛгАВпЉСеАЛеЄЂеЫ£зіДпЉШпЉРдЇЇгБЃеЗЇиЇЂеЬ∞гАБж∞ПеРНгВТи®ШеЕ•гБЧгАБгАМжИ¶еПЛе≠ШеСљжЙЛеЄ≥гАНгВТдљЬгБ£гБЯгБУгБ®гВТи®Љи®АгБЧгБЯгАВ
йШ™еП£гБХгВУгБѓгАБгАМгБУгБЃи≤ійЗНгБ™жЙЛеЄ≥гВТгАБиґ≥гБЃгБµгБПгВЙгБѓгБОгБЂеЉµгВКдїШгБСгАБгВ≤гГЉгГИгГЂгБІгБЧгБ£гБЛгВКгБ®еЈїгБНдїШгБСгБ¶гАБеЄ∞еЫљгБЃйАФгБЂгБ§гБДгБЯгАВгБУгВМгБѓжЧІгГїгВљйА£еЕµгБЂи¶ЛгБ§гБЛгВЛгБ®гАБеН≥гАБйКГжЃЇгБХгВМгВЛж±Їж≠їгБЃи°МеЛХгАВдЊЛгБЂгВВгВМгБЪгАБйШ™еП£гБХгВУгБѓгАБгВљйА£гГКгГЫгГИгВЂжЄѓгБІгАБжЧІгГїгВљйА£еЕµгБЛгВЙиЇЂдљУж§ЬжЯїгВТеПЧгБСгБЯгБМгАБйШ™еП£гБХгВУгБѓељУжЩВгАБгБЖгВЙиЛ•гБДе∞СеєігАВжЧІгГїгВљйА£еЕµгБѓгАЭгБКгБДе∞СеєігАБжЧ©гБПи°МгБСгАЯгБ®гАБгБЖгБЭгБЃгВИгБЖгБЂз∞°еНШгБЂйАЪгБХгВМгАБеЊ©еУ°иИєгБІдєЭеЈЮгГїдљРдЄЦдњЭжЄѓгАБгБЭгБЧгБ¶еИЧиїКгБІйГЈйЗМгГїж©ЛжЬђгБЂеЄ∞йВДгБЩгВЛгБУгБ®гБМгБІгБНгБЯгАНгБ®и™ђжШОгАВгАМжИ¶еПЛгБЃеЃЯеЃґгБЃйЫїи©±гВТзЙЗгБ£зЂѓгБЛгВЙи™њгБєгАБжИ¶еПЛгБМеЕГж∞ЧгБІгБДгВЛгБУгБ®гВТдЉЭгБИгБЊгБЧгБЯгАВеЃґжЧПгБѓгАБгБЭгВМгБѓгВВгБЖе§ІеЦЬгБ≥гБІгБЧгБЯгАНгБ®и™ЮгБ£гБЯгАВ
иБіиђЫиАЕгВЙгБѓгАБеЕµе£ЂгБМгАЭгБµгВЛгБХгБ®гАЯгВТж≠МгБ£гБ¶жБѓзµґгБИгБЯи©±гБЂгБѓгАБгВЈгГЉгГ≥гБ®иБігБНеЕ•гБ£гБ¶зЫЃй†≠гВТзЖ±гБПгБЧгАБ冱еСКгБМзµВгВПгВЛгБ®гАБгАЭжИ¶еПЛе≠ШеСљжЙЛеЄ≥гАЯгВТжЙЛгБЂгБ®гБ£гБ¶зЬЇгВБгБ™гБМгВЙгАБжИ¶дЇЙгБЃжЃЛйЕЈгБХгВТгБЧгБњгБШгБњгБ®жДЯгБШгБ¶гБДгВЛжІШе≠РгБ†гБ£гБЯгАВ
дїКеЫЮгАБеИЭгВБгБ¶йШ™еП£гБХгВУгБЃжȶ决冱еСКгБЃгВҐгВЈгВєгВњгГ≥гГИељєгВТеЛЩгВБгБЯ汆ж∞ЄгБХгВУгБѓгАБгАМгВЈгГЩгГ™гВҐжКСзХЩзФЯжіїгБЃеРДгВЈгГЉгГ≥гВТеЖЩзЬЯгБІи¶ЛгБ¶гБДгБЯгБ†гБДгБ¶гАБйШ™еП£гБХгВУгБЃи©±гВВгВИгБПгВПгБЛгБ£гБЯгБ®жАЭгБДгБЊгБЩгАНгБ®ињ∞гБєгАБгАМдїКеЊМгВВгАЭйїТе≠РељєгАЯгБ®гБЧгБ¶еНФеКЫгБЧгБЯгБДгАНгБ®и©±гБЧгБЯгАВ
йШ™еП£гБХгВУгБѓгАМгБ©гВУгБ™гБЊгБУгБ®гБЧгВДгБЛгБ™зРЖе±ИгВТдЄ¶гБєгБЯгБ®гБУгВНгБІгАБдЇЇгБ®дЇЇгБ®гБМгАБгБКдЇТгБДеСљгВТе•™гБДеРИгБЖгБУгБ®гБ™гВУгБ¶гАБжЦ≠гБШгБ¶и®±гБХгВМгВЛгВВгБЃгБІгБѓгБВгВКгБЊгБЫгВУгАВзІБгБЃе†±еСКгВТиБЮгБЛгВМгБЯжЦєгАЕгБѓгАБгБЬгБ≤гАБжђ°дЄЦдї£гБЃжЦєгАЕгБЂжИ¶дЇЙгБЃжВ≤жГ®гБХгВТи™ЮгВКзґЩгБДгБІгБДгБЯгБ†гБНгБЯгБДгАНгБ®и®ігБИгБ¶гБДгБЯгАВ
еЖЩзЬЯпЉИдЄКпЉЙгБѓжȶ决冱еСКгВТгБЩгВЛйШ™еП£гБХгВУгАВеЖЩзЬЯпЉИдЄ≠пЉЙгБѓйШ™еП£гБХгВУгБЃжȶ决冱еСКгБЂйЫЖгБЊгБ£гБЯе§ІеЛҐгБЃиБіиђЫиАЕгБЯгБ°гАВеЖЩзЬЯпЉИдЄЛпЉЙгБѓдїКеЫЮгБЃе†±еСКгВТжОІгБИгАБжЇЦеВЩгВТйА≤гВБгБЯйШ™еП£гБХгВУпЉИеП≥пЉЙгБ®ж±†ж∞ЄгБХгВУгАВ