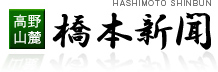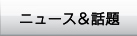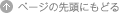ニュース & 話題
「空海と高野山」ゆかいに講演~郷土史家・瀬崎さん
高野山真言宗の開祖・弘法大師について語る講演会「空海と高野山」が、郷土史家・瀬崎浩孝さんを講師に、和歌山県橋本市城山台の紀見地区公民館で開かれた。瀬崎さんは「空海は鎮護国家、万民快楽などを求めて、高野山を開いた」と話し、「私も高野山麓の1市民として、最近では、手を合わせたり、ありがとうと謝辞をのべたり…」と、愉快に語った。
会場には「仏像の変遷」と題して、推古朝~鎌倉時代の仏像写真約30枚や、空海の思想、金剛界・胎蔵界の両界曼荼羅図(りょうかいまんだらず=悟りの世界)などを掲示。講演では、スライドも使いながら行われ、大勢の市民が楽しく聴き入った。
瀬崎さんは、「空海は香川県生まれで、京都で勉強したのに、なぜ真言密教の本拠地に和歌山・高野山を選んだのか。そこは標高約900メートルの山なのに」と、疑問符を提示。「そこには壇上伽藍(だんじょうがらん=根本大塔、金堂、御影堂など配置)を築いて、奥の院には庶民、大名の墓石群があります」と、山上の様子を説明した。
そのうえで、「高野山の山上盆地から、周囲を見渡すと、8つの峰があり、それはまさに蓮(はす)の花のような形である」と説明。唐の国から三鈷を投げると高野山の松に落ち、開創したという〝三鈷の松(さんこのまつ)〟の言い伝えもまじえながら、「空海は、地勢や飲料水調査などを十分に行ったうえで、目的達成への最適地であることを立証した」と述べ、「丹生明神から神領寄付の託宣をいただいて、高野山を開いた」と話した。
また、「時代は進み、戦国時代には応其上人(おうごしょうにん)の父が、信長に堺の鉄砲を融通。後に豊臣秀吉が高野山攻め考えた際、応其上人が嘆願すると、父の恩義を覚えていた秀吉が、高野山攻めを断念した」と開設。橋本の紀ノ川に橋を架け、塩市を開き、郷土を繁栄させた応其上人についても、わかりやすく紹介した。
講演の後、市民らが次々と質問を受けた瀬崎さんは、「空海は鎮護国家、万邦平和、万民快楽を祈って修行しました。自ら入定留身(にゅうじょうるしん)して、最高の浄土(曼荼羅の世界)を設定するために、高野山を開創した」と、丁寧に話していた。