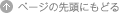特集
今も恩師を慕い、アマ・画家に徹す 日本画家・山内清治さん(69)(橋本市下兵庫)
あれはもう50年も昔の記憶。大阪は、南海高野線の「帝塚山駅」。目鼻立ちの整った、着物姿の、50歳代の紳士が、いつも夕刻、よく改札口を通った。前で組み合わせた両手には、いつもハンカチをかぶせていた。全身から発散する、その不思議なオーラ。当時、改札係だった山内さんが思わず聞く。「あの人は、いったい、だれ?」。すると同僚が「知らないの? あの人こそは、日本一偉い、絵描きさんや」と言う。何と、それは「当代、美人画を描かせたら、右に出るものはいない」と評判の、日本美術院理事、中村貞以(なかむら・ていい)画伯(1900~1982)だった。
中村画伯は幼い頃、両手に火傷(やけど)を負い、両手が「板」のように固くなった。このため、絵を描くときは、両手のひらで筆を挟んだ。絵を描くときの、その独特の動作を称して、画壇では「拝み描き」とも、「合掌描き」とも呼んだ。身体的な障害を克服し、独自の画境を開いた、稀有(けう)な人である。その中村画伯が、帝塚山駅近くの一軒家に住んでいた。山内さん自身、小学生時代、絵画コンクールで入選。県立橋本高校では、選択の時間に美術をとった。絵は大好きだ。「そんな偉い先生が、すぐ近所にいる。ぜひ教えてもらおう」。そう決意して、何度も門を叩いたが、簡単には入れてくれない。断られ、また断られ、断られ…。1961年2月に、やっと内弟子にもぐりこんだ。
当時、中村画伯は、妻と娘、妻の妹との4人暮らし。主宰する「春泥会」には、通いの約60人の弟子がいた。山内さんは、橋本駅前の自宅から電車で通勤。しかし、夜勤明けには、滅多に自宅に帰らず、ひたすら師匠の家へ通う。師匠は、他の弟子には直接、絵画指導しても、山内さんには一切教えない。「絵は自分で描きなさい。ここにいる間に、絵描きの生活を学びなさい」と言うだけだった。それでも、山内さんには、一部屋を貸し与え、ただ1人、アトリエにも入れた。その代わり、炊事、洗濯、風呂焚き、掃除、庭の手入れ…と、身の回りの世話をさせる。また、庭の鉢植えの花の写生、奈良の東大寺・三月堂の女神像の写生など、いつでも気軽に同伴させる。山内さんは、先生の両手のひらに、おずおずと絵筆を差し出し、先生の「拝み描き」の前に、スケッチブックを広げる。身じろぎもせず、息を止めて、キャンバスになった。そのときの先生の息遣い、対象への眼差し。徐々に仕上がっていく作品。先生の心の動きを、ひしひしと感じ、真っ先に作品を見ることができた。それだけでも至福だったが、「写生は、模写とは違う。生きたものを写すのや」と、絵の真髄を吹き込んでくれた。
山内さんは橋本市古佐田生出身。4歳で母を、10歳で父を、病気で亡くした、世に言う薄幸の境遇。大学進学はあきらめざるを得なかった。しかし、中村画伯の、いわば「書生」になったことで、わずか数年後には、その努力が見事結実する。
1964年に姉の嫁ぎ先の奈良・大和郡山の金魚の養殖風景を描いた「養魚場」、65年には、記憶にない両親との生活を思い描いた「川漁師」、66年にも日本一のヘラ竿(さお)の本場の姿を描いた「竿工場」が、いずれも日本美術院展で入選。その年の9月には「院友」に推挙された。若干22才で、押しも押されもしない、日本画家となったのである。とくに地元、紀ノ川で川魚を取り、生計を立てていた父の「川漁師」の絵は、網を繕う筋骨隆々とした父と、そばで赤ん坊(山内さん)を抱く母の雰囲気が、ほのぼのと活写されている。誰もが認める実力だった。でも、山内さんは「いろいろと思うところがあって」間もなく、内弟子を辞めた。アマチュア画家を志し、60歳で南海電鉄を定年退職するまで、いや、その後も、いわゆる「日曜画家」に徹したのである。
山内さんの、郷土における、文化貢献は著しい。64年に橋本・伊都地方の絵描きを集めて「橋本絵画同好会」を旗揚げした。第1回展の出品者は、たった10人だったが、今は、会員も63人に増えた。もちろん、指導者も大勢育ち、若い後進の面倒を見ている。94年には、同市胡麻生の相賀(おうが)八幡神社から、「3年後に正遷宮(せんぐう)奉祝祭がある。本殿の壁画を、お願いしたい」と依頼があった。山内さんは快諾。大きな板に下絵を描き、最終段階で弟子7人を加え、完成させた。壁画の大きさは約8メートル四方もあり、本殿の四方の壁に取り付けた。絵は、守り神の朱雀、聖獣の麒麟(きりん)、白虎、青竜、玄武、それに白い神馬や、剣をかざす武者など。まばゆいばかりの極彩色だ。正遷宮は喜びのうちに営まれた。今は、毎年、干支(えと)の大絵馬を制作、奉納。参拝者を魅了している。また、自宅近くには、日本画の塾「鬼灯庵」を設けて、弟子たちを指導。橋本市文化協会長なども歴任し、昨年には、橋本市文化賞を受賞した。師匠に諭された、ほんものの「絵描きの生活」を、いまだ探求してやまないのである。
あれは、「院友」に推挙されたばかりの頃。市の美術展に「石垣上の数件の民家」の絵を出展した。「何これ、この絵、偽もんや」と、50がらみの男がつぶやく。山内さんが、何度も民家に通い、丹念に描いた民家の風景。「院友」になったばかりの、傲慢さが、自分を抑えられない。「どこが偽物か」と口調も荒かった。「この絵の石垣では、簡単に崩れてしまう。本物の石垣は、石ひとつ抜いても、他の石が支え合い、崩れんもんや」と、鼻先で笑った。ずっと後になって、土木専門家に「石垣は『田』の形には積まない」と教えられ、「ああ、あの男は、ベテランの石垣職人だったか」と、自分の「節穴の目」を、改めて思い知らされる。中村画伯が「写生は模写やない」と言われたことが、その時、やっとつかめて、目からうろこがおちた。
また、あれは、中村画伯の内弟子になって間もない頃。師匠は夕方になると、大阪の繁華街へ出かける。寂しがり屋で、1人で酒を飲みに。帝塚山駅の改札口を、夕刻になると通るのは、そのためだった。夜9時すぎに帰宅し、すぐに眠られる。山内さんは、何か用事があったらいけないので、枕元で正座している。師匠はだいたい2時間後に目を覚まし、「もう、寝えや」と言ってくれた。よく働いたが、給金はなかった。それでも、毎年、正月には「お年賀に」と、山内さんに直筆の色紙を持たせた。山内さんは、師匠の後援者宅を回る。医師や会社社長、商店主らに、「師匠からです」と挨拶して、色紙を渡す。すると、誰もが2000~3000円の現金をくれた。合わせて60000円ぐらい。帰って師匠に渡すと、師匠は「そうか、いただいておきなさい」と、全部くれた。南海電鉄での山内さんの月給が8000数百円程度の時代。とても大金で、うれしかった。「絵画修行をして、お金までもろうて」と思う。
あれから、早や半世紀。もう、中村画伯も、奥さんも、お嬢さんも、この世にはいない。山内さんの口から「寂しいです」という言葉がもれた。それでも、山内さんには、5年間、師匠のそばで暮らした、貴重な思い出がある。愛弟子だった自負がある。そして今も、院展が大好きだ。院展の「人の影を踏む勿(なかれ)、己の影も踏む勿」という言葉が好きだ。山内さんは、まるで、それを実践するように、「私は絵を売らない」と断言。誰に対しても、絵を売らないできた。それどころか、最近では、自分の絵400点のうち、350点もの労作を焼却処分にした。あくまでも、アマチュア画家に徹する山内さん。「生涯、師と仰ぐのは、中村先生」と、きっぱり言い、「自然に、素朴に、絵画人生を送りたい」と、しめくくった。
(2011年3月19日 曽我一豊)